褐色矮星の風速を初測定、秒速650m
【2020年4月16日 NASA JPL/アメリカ国立電波天文台】
米・バックネル大学のKatelyn Allersさんたちの研究チームが、しし座に位置する褐色矮星「2MASS J10475385+2124234」(以下、2MASS J1047+21)の風速を計測し、秒速約650m(時速約2300km)であるとする研究成果を発表した。褐色矮星の風速が計測されたのは初めてのことで、太陽系内最速である海王星の風速である秒速約560m(時速約2000km)を超えていることを示している。
褐色矮星とは、質量が太陽系最大の惑星である木星の13倍以上はあるものの、核融合反応を維持して輝き続けることができない、惑星と恒星の中間的な存在である。その主成分は木星や太陽と同じくほぼ全てガスであり、固い地面は存在しない。そのような天体の「風」は、固体の地面を持つ地球のような天体の風とは指すものが微妙に異なっている。
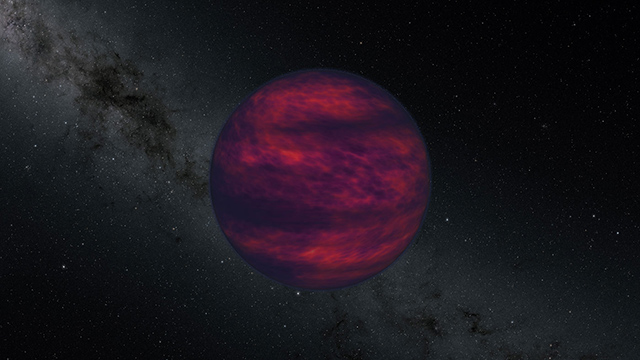
褐色矮星の想像図(提供:NASA/JPL-Caltech)
褐色矮星の上層ではガスが比較的自由に動けるが、ある程度より深くなると気圧が非常に高くなり、ガスが一体となって固体の球のようにふるまう。この褐色矮星の内部と見なせる部分は自転していて、上層の大気は基本的にそれに引きずられて動く。この内部と上層の間に生じるわずかな速度差が、褐色矮星の「風」である。
Allersさんたちは今年1月30日にミッションを終了したばかりのNASAの赤外線天文衛星「スピッツァー」と地上の電波望遠鏡の観測結果を組み合わせることにより、この「風速」を測定した。
2MASS J1047+21の大気は摂氏600度を超えており、大量の赤外線が放射されている。また、この天体までの距離は約32光年で地球から比較的近い。そのおかげで、2MASS J1047+21表面の大気が動くことによる赤外線の変化をスピッツァーの観測で検出することができ、大気の移動速度を知ることが可能となった。
一方、2MASS J1047+21内部の回転速度を決定するため、研究チームは天体の磁場に注目した。最近の研究で、褐色矮星の内部で強力な磁場が発生することが知られているが、この磁場が褐色矮星内部の回転と共に動くと荷電粒子が加速されて電波が発生する。研究チームは2MASS J1047+21が発する電波をカール・ジャンスキー超大型干渉電波望遠鏡群(VLA)で観測し、その結果から内部の回転速度を求めた。
褐色矮星の上層大気(赤色、回転周期は1.741時間)と内部(灰色、回転周期は1.758時間)との比較から風(水色)の速度を求めた手法の紹介動画。木星は比較として描かれている(提供: Bill Saxton, NRAO/AUI/NSF)
研究チームはこの手法の精度を評価するために、褐色矮星と内部構造が近いガス惑星の木星でも同じ分析を行っている。2MASS J1047+21同様、赤外線の観測データから木星の上層大気の速度を調べ、電波観測から内部の回転速度を求め、そこから風速を計算した。これを、木星に接近した探査機からの正確な観測データと比較したところ、正しい結果が得られていた。一定の条件が必要ではあるが、この手法が他の褐色矮星や系外ガス惑星にも適用できることを示している。
「この手法は、系外惑星の大気のダイナミクスを深く理解する上で非常に貴重だと考えています。とりわけワクワクするのは、化学と大気のダイナミクス、そして天体を取りまく環境がどのように関わり合っているかがわかること、そしてこれらの世界に関する包括的な知見が得られる見通しがあることです」(Allersさん)。
〈参照〉
- NASA JPL:In a First, NASA Measures Wind Speed on a Brown Dwarf
- NRAO:Astronomers Measure Wind Speed on a Brown Dwarf
- Science:A measurement of the wind speed on a brown dwarf 論文
〈関連リンク〉
- Spitzer Space Telescope:
- カール・ジャンスキー超大型干渉電波望遠鏡群(VLA)
関連記事
- 2026/01/21 スーパーアースの「地下のマグマ海」が地球外生命をはぐくむかも
- 2026/01/14 観測で初の裏付け、生まれたての惑星たちはふわふわ
- 2025/12/08 すばる望遠鏡OASIS計画の初成果、巨大惑星と褐色矮星を発見
- 2025/12/05 超小型紫外線衛星「モーヴ」打ち上げ成功、恒星フレアをモニター観測
- 2025/11/14 ホットジュピターの静かな誕生に迫る
- 2025/10/28 地上と宇宙の望遠鏡が共同、赤色矮星を周回する褐色矮星を発見
- 2025/09/16 黒点を横切る惑星が伝える、傾いた惑星系の姿
- 2025/09/11 高密度星団形成領域における星形成活動の全貌
- 2025/08/29 原始惑星系円盤のすき間を公転する系外惑星を発見
- 2025/08/26 赤色矮星2個と褐色矮星2個からなる四重連星系を発見
- 2025/05/08 exoALMAが明らかにした動的で複雑な惑星誕生の現場
- 2025/04/28 ハビタブル惑星の大気に“生命の証拠”分子の兆候
- 2025/01/22 ミニネプチューンの大気に多量の二酸化炭素を検出
- 2025/01/21 大気中にダイヤモンドが舞う系外惑星
- 2024/12/17 惑星の外側で塵が集まる様子をアルマ望遠鏡で観測
- 2024/11/18 超高密度スーパーアースとその形成過程の手がかりとなり得る外側の惑星を発見
- 2024/09/11 ホットジュピターの内側で、公転が大きく変動するミニ海王星
- 2024/07/29 「灼熱の土星」型の系外惑星で大気から水蒸気の証拠を検出
- 2024/06/18 想定外の軌道を持つ「ミニ海王星」を発見
- 2024/05/30 ローマン宇宙望遠鏡の系外惑星観測用コロナグラフが準備完了













![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)