月刊ほんナビ 2025年10月号
📕 「星の運動について知を重ねる人」
紹介:原智子(星ナビ2025年10月号掲載)
地動説を追い求める人々の物語『チ。─地球の運動について─』(魚豊・著)を読んでいると、あらためて「真理を求める人は、自分の抱いた謎を解かずにはいられない」と感じる。“誰のため”でも“何のため”でもなく、むしろ“誰に止められても”“何の役に立たなくても”知りたいと欲する。その姿勢こそ科学の原点だろう。今月は、そんな「宇宙の謎に向き合った人たち」の本を紹介しよう。
まずは、基本中の基本『ガリレオ』から。「まんがと知識でよく分かる!世界のスゴイ科学者」シリーズは台湾で大ヒットした書籍で、第1弾が『ガリレオ』と『ダーウィン』。どちらもその分野における知識構造を根幹から転換した科学者で、宗教にも影響を及ぼしている。このシリーズの特徴は、右から開くと「マンガ」で左から開くと「解説書」というハイブリッド式になっていること。小学生ならマンガでガリレオの生涯や研究について基礎を学び、高校生(あるいは基礎を理解した小中学生)は解説側を読んでさらに深く専門知識を得ることができる。ユニークで実践的な学習書。
次もマンガだが、こちらはフルカラーのデザイン画で描かれており、アート作品のように美しい。『マンガでわかる カルロ・ロヴェッリの物理学』は、相対性理論と量子論を統合する試み「ループ量子重力理論」の第一人者のロヴェッリと、視覚芸術家のルーカ・ポッツィの対話で進む超入門書(と本人たちは言う)。二人を包むラオスのジャングルさながらに「世界は石(もの)ではなくキス(できごと)の網の目でできている」とロヴェッリは説明する。アートを感じるように、まずはループ量子重力理論にふれよう。
『あなたと宇宙』は、2018年に亡くなったホーキング博士から幼い子どもたち=未来の科学者へ贈るメッセージが詰まった絵本。『星ナビ』読者なら、車いすに乗って合成音声で宇宙を説くホーキング博士の姿をすぐ思い出せるが、幼い子どもたちは彼を見ていない。そんな子どもたちの素朴な質問に答える形をとりながら、自分で考え、みんなで力を合わせ、素晴らしい未来をつくるために「まよったときには、星をみあげましょう」と語りかける。
ここからは、日本人が登場する本を3冊。まずは、歴史の中で天文が担った役割をひもとく『占いと中世人』。同書は2011年に講談社現代新書から発刊されたもので、良質な歴史書を掘り起こして広める「読みなおす日本史シリーズ」の一冊として今年あらためて配本された。日本の中世とは平安後期から戦国時代で、政治や合戦はもちろん日常生活でも占いが重視された。官人である陰陽師は天文学者の側面を持ち、暦を管理した。現在の国立天文台も「暦象年表」を発行することが重要な任務の一つだ。
次は、江戸後期の蘭学者で天文・物理・数学の翻訳を行った『志筑忠雄』。多彩な活動の中でも有名なのは、『暦象新書』を著して日本に初めてニュートン物理学を紹介したこと。地動説については彼の師である本木良永も書いたが、志筑は理論を理解したうえで持論をそえて「地動説」という訳語を創出した。そのほか「重力」「遠心力」など、いま私たちが使っている専門用語を造語し、さらに「鎖国」という言葉も生み出した。自然科学だけでなく、国際情勢にも慧眼を持っていた彼の生涯をつづった伝記。
『天文学者が1を知ると、宇宙は10の謎を投げかけてくる』は、現役天文学者9人が最新の研究でわかったことと、そこから新たに生まれた謎を紹介する解説書。取り上げるのは「恒星間天体」「系外惑星」「超巨大恒星フレア」「超高輝度超新星」「高速電波バースト」「重力波」「高エネルギーニュートリノ」「ブラックホール」「初期宇宙」。各章の扉に書かれた「1を知る」と「新たな謎」を意識しながら読もう。
これからも天文学を深く研究したいと思う人たちは必ず現れる。そのとき思う存分に研究できる社会であってほしいと、戦後80年を迎えて強く願う。権力に制限されることなく、天文学を自由に研究できることが「平和」なのだろう。
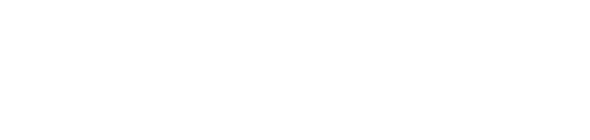
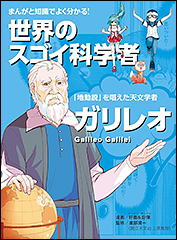
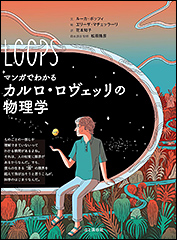
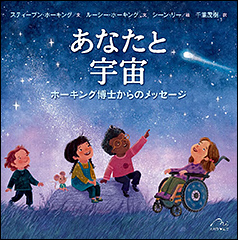


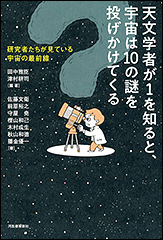












![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)