月刊ほんナビ 2025年7月号
📕 「梅雨空の下、星に思いをめぐらせる」
紹介:原智子(星ナビ2025年7月号掲載)
辻村深月氏の小説『この夏の星を見る』が映画化され、7月4日に公開される。原作は2023年に発刊された単行本で、本誌2023年8月号に掲載した作者インタビュー記事を覚えている読者も多いだろう。先日、試写を鑑賞したので映画作品の詳しいことは本誌2025年8月号で紹介しよう(天文ファンが思わずにんまりするシーンがたくさんあるからお楽しみに!)。
当コーナーでは、映画公開にあわせて6月に新たに発行される「角川文庫」版と「角川つばさ文庫」版について解説する。どちらも上下2巻に分かれ、手に取りやすいサイズ(文庫判・新書判)になった。物語は、コロナ禍を生きる中高校生たちが星空を通して全国の仲間と交流し、それぞれが悩みながら成長していく青春群像劇。角川文庫版には、前日譚である短編『薄明の流れ星』が収録され、宇宙飛行士の山崎直子さんによる「解説」も付いている。2年前に単行本を読んだ人も、この2編を読む価値はおおいにある。角川つばさ文庫版は小中学生を対象にしているシリーズなので全編にふりがなが振られ、ストーリーを理解しやすいよう随所に那流氏のイラストが添えられている。「高校生たちの天体観測」という場面がイメージしにくい子どもでも、無理なく読み進められるだろう。“この夏”はそれぞれの好みで原作を読み、映画館と夜空で“星を見る”のはいかが。
ここからは、SF小説を2冊紹介する。長くファンに愛されてきた不朽の名作『星を継ぐもの』シリーズから、待望の新巻にして最終巻『ミネルヴァ計画』の日本語訳がついに出た。過去作から続くおなじみのキャストも登場し、量子論の多世界解釈をベースに惑星ミネルヴァをめぐるスリリングな物語が展開する。SFらしい壮大なスケールと深い思想的テーマが融合した今作は、シリーズを締めくくるにふさわしい内容で、亡きホーガン自身の大団円といえよう。
一方、若々しい作品群が宮西建礼氏の『銀河風帆走』だ。著者が大学在学中の2013年に第4回創元SF短編賞を受賞した表題作をはじめ、書き下ろし1編を含む全5編を収録した短編集。同書は今年2月に第45回日本SF大賞特別賞も受賞し、活躍が期待される作家だ。短編『銀河風帆走』は、銀河系規模の破滅に陥った人類から「地球生物の未来」を託された“知的宇宙船”が、帆船のように宇宙を進みながら試練に立ち向かう話。そして、『されど星は流れる』では『この夏の星を見る』と同じようにパンデミック時代の高校天文同好会の活動を描いている。流星同時観測によって太陽系外から地球に飛び込んだ「系外流星」の観測に挑戦し、ネットワークを通じて多くの人たちと交流を広げる。こちらは人間の科学的探求心と未来への情熱が伝わる。なお、個人的な好みだが、ハードタッチな書影カバーを外したら仮フランス装で製本されていて、静かなぬくもりを感じた。
次の2冊は、天文学を鍵として文学を味わう書籍と雑誌。『星の王子さま88星座巡礼』は、「サン=テグジュペリが『星の王子さま』に込めた謎」をフランス語と日本語に精通した著者が読み解いていくガイドブック。日本語に慣用句や掛詞があるように、フランス語で書かれた原書にはフランスの文化が刻まれている。この本では、星の王子さま自身が『星の王子さま』という物語に登場する天体やキリスト教の暦を手がかりにして、「星の王子さまはハレー彗星であり、作者はその地球接近日(1986年4月11日)を予測していた」と紹介する。『星の王子さま』の奥深さを再認識させてくれる一冊。
旅とポエジーをテーマに各地をめぐる『たびぽえ』2025前期号(VOL.9)の特集は「宇宙」。JAXA相模原キャンパス、キトラ古墳、宮沢賢治の故郷・花巻など、天文の香り漂う場所が続々登場。当誌連載中の「オリオンと猫」の舞台である大佛次郎記念館もバッチリ紹介されている。旅と宇宙をつなぐ、新感覚の文芸情報ムック。
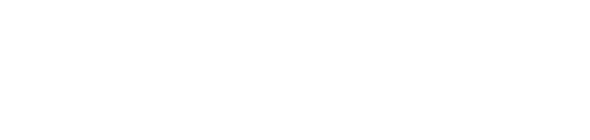
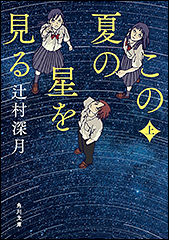
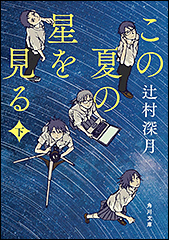
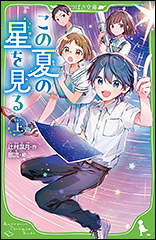

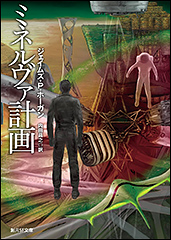
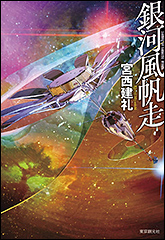














![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)