月刊ほんナビ 2025年11月号
📕 「望遠鏡が映し出す宇宙の細部」
紹介:原智子(星ナビ2025年11月号掲載)
長くて“熱い”夏がようやく過ぎ、「秋の夜長」を感じられる季節になった。「読書の秋」でもある今月は、巨大望遠鏡や宇宙望遠鏡がとらえた天体写真集を紹介しよう。
まずは、日本が世界に誇るすばる望遠鏡の25周年を記念して刊行された『すばる望遠鏡 宇宙の神秘を探る』。ご存じのとおり、すばる望遠鏡は日本が初めて国外に設置した本格的な天文観測施設で、世界最大級の一枚鏡をもつ光学赤外線望遠鏡だ。同書では1999年のファーストライト(試験観測開始)と2000年の共同利用観測開始から現在までの歩みを振り返り、未公開のものを含む多数の天体画像を収載している。超広視野主焦点カメラ(Hyper Suprime-Cam)で撮影された超銀河団の微細な光点や、若い恒星を取り巻く原始惑星系円盤の散乱光など、貴重な画像は研究の最前線で活用されてきた。国立天文台内外の執筆陣による解説に加え、運用の現場や今後の役割にもふれる、すばる望遠鏡の成果を凝縮した一冊。
次は、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)によるビジュアル本を2冊。ハッブル宇宙望遠鏡(HST)の後継機として2021年クリスマスに打ち上げられたJWSTは、鮮明な画像を次々に届けている。特に『ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡のすべて』の表紙を飾る「創造の柱(わし星雲にある柱状のガス塊)」は、HSTとは段違いの超高解像で、まるで自分がその場で目撃しているかのような“想像”をかき立てられる。そんなJWSTの開発秘話や観測技術、最新の研究成果を解説するのがこの本。JWSTの目標は「原初の宇宙」を解析することだという。従来の望遠鏡では見ることが難しかった赤外線での観測が、宇宙誕生や惑星形成をどのように明らかにするのか図解も交えながら伝える。
2022年7月にJWSTが最初の画像を届けたときNASA長官のビル・ネルソンは「人類がこれまでに見たことのない画期的で新しい宇宙の景色を披露する」と言った。その言葉どおり『見たこともない宇宙』には、今まで見ることができなかった赤方偏移した光をとらえた画像が詰まっている。遠方からやって来る波長の伸びた光を見ることで、宇宙の始まりに近づくことができる。JWSTの性能紹介とともに、「古い宇宙」の「新しい姿」を英国宇宙庁宇宙科学部門長が丁寧に解説する。
次の2冊は、スミソニアン協会が関わった大型の宇宙図鑑。スミソニアン協会は、英国人科学者スミソンの遺志により「人類の知識の増進と普及」を目的に米国で設立された世界最大級の学術文化研究機関。多くの博物館や研究所を運営し、膨大な文化・科学資料を保存公開している。その資料の中から、航空宇宙博物館のコレクション・学芸担当副館長を務めたラウニウス氏が選び著したのが『スミソニアン 宇宙大図鑑』だ。
一方、『COSMOS 美しき宇宙の図鑑』はスミソニアン協会監修でまとめられたもの。こちらは巻末80ページに紹介された88星座が目を引く。美しい古典彩色星図と、その星座にある星雲星団の最新写真のとりあわせが見事。2冊とも約400ページのフルカラーで、掲載写真も600点以上とたっぷり。豪華な図鑑のため、家庭で両書を備えることは難しいだろう。図書館などで実物を手にとり、ページをめくり、見比べて、好みを選ぶといいかもしれない。
最後は、ぐっと近い天体である月にぐっと寄った『月面フォトアトラス』。本誌で過去に連載した「月ナビ」(2019年2月~、全20回)を担当した白尾元理氏が撮影した精細な月面写真をもとに、そこに写っている地形を詳しく案内するガイドブック。実際に双眼鏡や天体望遠鏡で観察しやすいよう月齢や月面エリアに分けて、月の地形(クレーター・山脈・谷など)と地質をわかりやすく示している。さらに、撮影テクニックと写真データも公開しているので「自分もこんな月面写真に挑戦したい」と思う人にとってありがたい教本でもある。
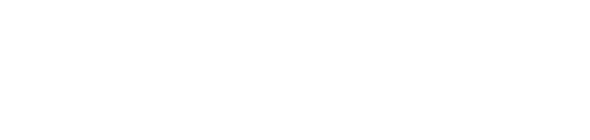

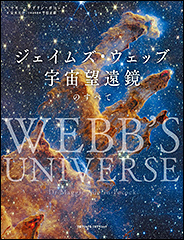
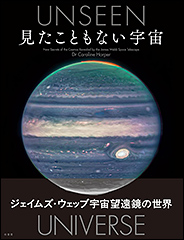
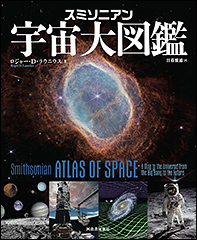
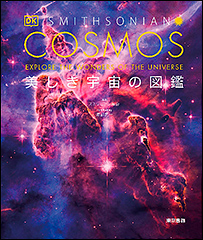
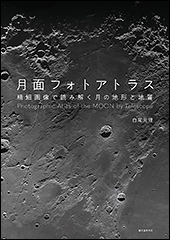













![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)